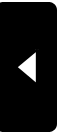2016年12月21日
12月のトピックス
◆自民党、時間外労働に罰則付き上限設ける方針 2016/12/12
自由民主党は、多様な働き方の実現を目指して、党内の「働き方改革に関する特命委員会」で議論を進めていますが、年内に中間報告を取りまとめるとのことです。その中で長時間労働の是正に向けて、労働基準法を改正し、時間外労働に罰則付きの上限を設けることなどを打ち出す方針を固めたということです。
◆日本年金機構 来年の「届書作成プログラム」「仕様チェックプログラム」公開 2006/12/12
日本年金機構より平成29年1月4日から利用開始となる「届書作成プログラム」と「仕様チェックプログラム」が公開されました。
【届書作成プログラムをご利用される皆様へ】
平成29年1月4日から利用開始となる届書作成プログラムの公開について
≫ http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/0901.html
【届出システムを自社開発または市販ソフトを使用している皆様へ】
平成29年1月4日から利用開始となる仕様チェックプログラムの公開について
≫ http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/0901-02.html
◆与党、税制改正大綱を決定 2016/12/09
新聞やニュースでも大々的に取り上げられていましたが、今月8日、自民・公明両党は「2017年度税制改正大綱」を決定しました。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
◆「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問・答申(厚労省)
【省令改正案のポイント】
1 通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件の撤廃
2 勤務間インターバルの導入促進のため、中小企業事業主に対して導入経費の一部を助成する制度の創設
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html
◆雇用保険制度の見直しについて報告書を公表 厚生労働省 2016/12/06
厚生労働省は5日、労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)において議論を進めている雇用保険制度の見直しについて、報告書をまとめ公表しました。
見直しに向けて議論が進められているのは、
・基本手当の水準及び平成28年度末までの暫定措置の在り方
・財政運営(雇用保険料率・国庫負担)の在り方
のほか、就職促進給付・教育訓練給付・育児休業給付の拡充などです。
自由民主党は、多様な働き方の実現を目指して、党内の「働き方改革に関する特命委員会」で議論を進めていますが、年内に中間報告を取りまとめるとのことです。その中で長時間労働の是正に向けて、労働基準法を改正し、時間外労働に罰則付きの上限を設けることなどを打ち出す方針を固めたということです。
◆日本年金機構 来年の「届書作成プログラム」「仕様チェックプログラム」公開 2006/12/12
日本年金機構より平成29年1月4日から利用開始となる「届書作成プログラム」と「仕様チェックプログラム」が公開されました。
【届書作成プログラムをご利用される皆様へ】
平成29年1月4日から利用開始となる届書作成プログラムの公開について
≫ http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/0901.html
【届出システムを自社開発または市販ソフトを使用している皆様へ】
平成29年1月4日から利用開始となる仕様チェックプログラムの公開について
≫ http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/0901-02.html
◆与党、税制改正大綱を決定 2016/12/09
新聞やニュースでも大々的に取り上げられていましたが、今月8日、自民・公明両党は「2017年度税制改正大綱」を決定しました。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
◆「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問・答申(厚労省)
【省令改正案のポイント】
1 通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件の撤廃
2 勤務間インターバルの導入促進のため、中小企業事業主に対して導入経費の一部を助成する制度の創設
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html
◆雇用保険制度の見直しについて報告書を公表 厚生労働省 2016/12/06
厚生労働省は5日、労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)において議論を進めている雇用保険制度の見直しについて、報告書をまとめ公表しました。
見直しに向けて議論が進められているのは、
・基本手当の水準及び平成28年度末までの暫定措置の在り方
・財政運営(雇用保険料率・国庫負担)の在り方
のほか、就職促進給付・教育訓練給付・育児休業給付の拡充などです。
2016年12月12日
「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果
★テーマ★「過重労働解消相談ダイヤル」に合計で712件の相談
厚生労働省が、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として11/6に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果をまとめ、公表しました。
今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で712件の相談が寄せられ、相談内容としては、「長時間労働・過重労働」に関するものが340件(47.7%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が305件(42.8%)だったとのことです。
下記で詳細をご紹介します。
★相談結果の概要★
◇相談件数 合計712件
◇主な相談内容
(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数712件に対する割合。 なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)
・長時間労働・過重労働 340件(47.7%)
・賃金不払残業 305件(42.8%)
・休日・休暇 53件 (7.4%)
◇相談者の属性 (括弧内は相談件数712件に対する割合)
・労働者 432件(60.7%)
・労働者の家族 199件(27.9%)
・その他 81件(11.4%)
◇主な事業場の業種 (括弧内は相談件数712件に対する割合)
・製造業 103件(14.5%)
・保健衛生業 101件(14.2%)
・商業 89件(12.5%)
◇「過重労働解消相談ダイヤル」では、次のような対応を行ったということです。
・相談者に労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明
・相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介
★まとめ★
上記の結果は、私たち社労士としてはさほど目新しいものではありません。しかしながら、経営者の皆様には、「1日だけの相談ダイヤルに、712件も相談があった」「やはり電通の話などもあって、長時間労働について問題意識を持っている社員や家族は多いようだ」など、気になる情報だと思います。
特に最後の「相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介」という部分は、「つまり、社員が相談ダイヤルにかけると、労基署のチェックが入ったり、下手をすると、あっせんや労働審判などにつながりかねない。」「外に相談するより、まずは悩みや問題を社内に挙げられる仕組みや雰囲気づくりが大切」と気付いていただければ嬉しいです。
お気軽にご相談ください。
厚生労働省が、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として11/6に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果をまとめ、公表しました。
今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で712件の相談が寄せられ、相談内容としては、「長時間労働・過重労働」に関するものが340件(47.7%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が305件(42.8%)だったとのことです。
下記で詳細をご紹介します。
★相談結果の概要★
◇相談件数 合計712件
◇主な相談内容
(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数712件に対する割合。 なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)
・長時間労働・過重労働 340件(47.7%)
・賃金不払残業 305件(42.8%)
・休日・休暇 53件 (7.4%)
◇相談者の属性 (括弧内は相談件数712件に対する割合)
・労働者 432件(60.7%)
・労働者の家族 199件(27.9%)
・その他 81件(11.4%)
◇主な事業場の業種 (括弧内は相談件数712件に対する割合)
・製造業 103件(14.5%)
・保健衛生業 101件(14.2%)
・商業 89件(12.5%)
◇「過重労働解消相談ダイヤル」では、次のような対応を行ったということです。
・相談者に労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明
・相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介
★まとめ★
上記の結果は、私たち社労士としてはさほど目新しいものではありません。しかしながら、経営者の皆様には、「1日だけの相談ダイヤルに、712件も相談があった」「やはり電通の話などもあって、長時間労働について問題意識を持っている社員や家族は多いようだ」など、気になる情報だと思います。
特に最後の「相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介」という部分は、「つまり、社員が相談ダイヤルにかけると、労基署のチェックが入ったり、下手をすると、あっせんや労働審判などにつながりかねない。」「外に相談するより、まずは悩みや問題を社内に挙げられる仕組みや雰囲気づくりが大切」と気付いていただければ嬉しいです。
お気軽にご相談ください。
2016年12月03日
出産を機に辞める??
★テーマ★ 「出産を機にやめる」は10年前の24.5%から6.9%に
厚生労働省が先日、同じ集団を対象に毎年実施している「21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」の第4回(平成27年)と「21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」の第14回(平成27年)の結果を取りまとめ、公表しました。
下記でその調査結果のポイントをご紹介します。
★調査結果のポイント★
◆1◆ この13年間の結婚の状況(平成14年成年者)
第1回調査(20~34歳)時に「結婚意欲あり」の独身者の方が、「結婚意欲なし」より、この13年間で結婚した割合が高い。
◇第1回調査時に独身だった者がこの13年間で結婚した割合
「結婚意欲あり」/「結婚意欲なし」
「男」 57.5%/21.2%
「女」 66.4%/29.0%
◆2◆ 独身女性の結婚後の就業継続意欲等(平成14年成年者・平成24年成年者)
独身女性の結婚後の就業継続意欲をみると、 10年前に比べ、「結婚した後も続ける」の割合は高くなり、「結婚を機にやめる」の割合は低くなっている。
◇「結婚した後も続ける」/「結婚を機にやめる」
14年成年者(第4回) 41.8% / 21.9%
24年成年者(第4回) 44.6% / 17.1%
「結婚した後も続ける」と回答した独身女性の出産後の就業継続意欲をみると、10年前に比べ、「出産した後も続ける」の割合は高くなり、「出産を機にやめる」の割合は低くなっている。
◇「出産した後も続ける」/「出産を機にやめる」
14年成年者(第4回) 51.3% / 24.5%
24年成年者(第4回) 65.1% / 6.9%
◇詳細は下記でご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen17/dl/gaikyou.pdf
★まとめ★
上記調査では、「出産を機にやめる」と答えた「24年成年者」は6.9%とあります。「24年成年者」というのは、今24歳ですから、まだ「出産」が自分事に感じられていないという可能性はあります。
14年成年者の現状などを知りたいところですが、残念ながらそのデータはありませんでした。
ただ一般的には、出産を機に仕事を辞める女性は6割ほどと言われています。
出産後も働き続けたいと思っても、様々な事情で辞めざるを得ない女性は多いということが伺えます。
優秀な人材を確保するヒントは、そんなところにもありそうです。
厚生労働省が先日、同じ集団を対象に毎年実施している「21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」の第4回(平成27年)と「21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」の第14回(平成27年)の結果を取りまとめ、公表しました。
下記でその調査結果のポイントをご紹介します。
★調査結果のポイント★
◆1◆ この13年間の結婚の状況(平成14年成年者)
第1回調査(20~34歳)時に「結婚意欲あり」の独身者の方が、「結婚意欲なし」より、この13年間で結婚した割合が高い。
◇第1回調査時に独身だった者がこの13年間で結婚した割合
「結婚意欲あり」/「結婚意欲なし」
「男」 57.5%/21.2%
「女」 66.4%/29.0%
◆2◆ 独身女性の結婚後の就業継続意欲等(平成14年成年者・平成24年成年者)
独身女性の結婚後の就業継続意欲をみると、 10年前に比べ、「結婚した後も続ける」の割合は高くなり、「結婚を機にやめる」の割合は低くなっている。
◇「結婚した後も続ける」/「結婚を機にやめる」
14年成年者(第4回) 41.8% / 21.9%
24年成年者(第4回) 44.6% / 17.1%
「結婚した後も続ける」と回答した独身女性の出産後の就業継続意欲をみると、10年前に比べ、「出産した後も続ける」の割合は高くなり、「出産を機にやめる」の割合は低くなっている。
◇「出産した後も続ける」/「出産を機にやめる」
14年成年者(第4回) 51.3% / 24.5%
24年成年者(第4回) 65.1% / 6.9%
◇詳細は下記でご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen17/dl/gaikyou.pdf
★まとめ★
上記調査では、「出産を機にやめる」と答えた「24年成年者」は6.9%とあります。「24年成年者」というのは、今24歳ですから、まだ「出産」が自分事に感じられていないという可能性はあります。
14年成年者の現状などを知りたいところですが、残念ながらそのデータはありませんでした。
ただ一般的には、出産を機に仕事を辞める女性は6割ほどと言われています。
出産後も働き続けたいと思っても、様々な事情で辞めざるを得ない女性は多いということが伺えます。
優秀な人材を確保するヒントは、そんなところにもありそうです。
2016年11月25日
「社会保険に関わる法改正」意識調査
先日、エン・ジャパン株式会社が、『エン派遣』上で、サイトを利用している20代以上の女性で、これまで社会保険に加入していない人を対象に「社会保険に関わる法改正」についてアンケート調査を行ない(1207名が回答)、その結果を公表しました。
ご存知のように、社会保険の適用範囲が10月から下記のように拡大しています。そのことがどれほど理解されているかなどの調査です。
★法改正の概要★
【これまでの加入対象】
労働時間が週30時間以上(正社員の4分の3以上の時間)に当てはまる方。
【2016年10月からの加入対象】※以下5つ全てに当てはまる方。
1.労働時間が週20時間以上
2.月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
3.勤務期間が1年以上の予定
4.勤め先の会社の従業員数が501人以上
5.学生または75歳以上ではない
★アンケート調査結果★
◇社会保険に関わる法改正について、詳細を知っている方は23%。
◇今回の法改正を受け、 5人に1人が「これまで社会保険に加入していなかったが、新たに社会保険の対象になり加入する」と回答。そのうち51%が「保険料の負担増のため働き方を変更した」と回答。
◇改正後も社会保険に加入しない働き方を選択すると回答した方のうち、24%が「加入対象から外れるために時間や収入を減らすよう働き方を変更」。
◇法改正について「経済的な負担が増える」ことへの不安多数。
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます。
http://corp.en-japan.com/newsrelease/2016/3415.html
★まとめ★
5人に1人が「これまで社会保険に加入していなかったが、新たに社会保険の対象になり加入する」と回答し、そのうち約半数が、保険料が増えるために、労働時間を増やすなど、収入が増えるように調整した、という結果だったということ。
社会保険加入の対象にならないよう、今より労働時間を減らすという人がいる一方で、収入を増やすために働き方を変えたいと思う人もいるわけですね。
この秋の改正では、対象は大企業だけですが、今後、中小企業にも広がっていくものと思われます。そのときは、やはり非正規で働いている社員一人ひとりが、「社会保険にどうせ入るのなら、もっと働きたい」と思っているのか、「それでも扶養の範囲に収まるように、収入や労働時間を減らしたい」と思っているのか、意向をよく把握することも大切になりそうです。
今後のパート・アルバイトの採用計画の話などと合わせて、上記のデータを見せてみるといいかもしれませんね。
2016年11月19日
11月のトピックス
◆平成28年「賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を公表 厚生労働省
2016/11/18
厚生労働省は17日、平成 28 年「賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を取りまとめ、公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/index.html
◆年金受給資格、納付10年に短縮 改正法成立 2016/11/16
年金の受給資格を得るために必要な加入期間を現行の25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。
◆過重労働防止の徹底 経団連 2016/11/15
経団連は11月15日、会員企業に対して経営トップみずから過重労働の防止を徹底するよう要請しました。
◆LGBT職員に結婚・介護休暇 千葉市、全国初の導入へ 2016/11/11
千葉市は来年1月から、同性パートナーと同居する市職員が「結婚」休暇(パートナー休暇)や、パートナーやその両親らのための介護休暇を取得できる制度を新たに導入します。市によると、性的少数者(LGBT)の職員のための休暇制度の導入は、全国の自治体で初めてということです。
◆市の課長自殺「過重業務が原因」遺族側が逆転勝訴 2016/11/11
6年前、福岡県糸島市の課長がうつ病になって自殺したのは「過重な業務が原因だった」として、遺族が市に賠償を求めている裁判で、2審の福岡高等裁判所は「市と町の合併に伴う地元への説明などで、1か月の時間外勤務が100時間を超えていた」などとして、1審とは逆に遺族側の訴えを認め1,600万円余りを支払うよう命じました。
◆ストレスチェック実施促進のための助成金の申請期が延長に 2016/11/10
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が延長になりました。
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
◆定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴 2016/11/04
定年後に再雇用されたトラックの運転手が「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
◆年金受給資格の短縮法案が衆院本会議で可決 2016/11/02
年金が受け取れない人を減らすため、受給資格を得るのに必要な加入期間を、25年から10年に短縮する法案は、1日の衆議院本会議で、全会一致で可決されました。今国会で成立する見通しです。消費増税に先立って来年10月の支払い分から、年金の受給資格を得るのに必要な加入期間を、25年から10年に短縮するとしています。
2016/11/18
厚生労働省は17日、平成 28 年「賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を取りまとめ、公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/index.html
◆年金受給資格、納付10年に短縮 改正法成立 2016/11/16
年金の受給資格を得るために必要な加入期間を現行の25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。
◆過重労働防止の徹底 経団連 2016/11/15
経団連は11月15日、会員企業に対して経営トップみずから過重労働の防止を徹底するよう要請しました。
◆LGBT職員に結婚・介護休暇 千葉市、全国初の導入へ 2016/11/11
千葉市は来年1月から、同性パートナーと同居する市職員が「結婚」休暇(パートナー休暇)や、パートナーやその両親らのための介護休暇を取得できる制度を新たに導入します。市によると、性的少数者(LGBT)の職員のための休暇制度の導入は、全国の自治体で初めてということです。
◆市の課長自殺「過重業務が原因」遺族側が逆転勝訴 2016/11/11
6年前、福岡県糸島市の課長がうつ病になって自殺したのは「過重な業務が原因だった」として、遺族が市に賠償を求めている裁判で、2審の福岡高等裁判所は「市と町の合併に伴う地元への説明などで、1か月の時間外勤務が100時間を超えていた」などとして、1審とは逆に遺族側の訴えを認め1,600万円余りを支払うよう命じました。
◆ストレスチェック実施促進のための助成金の申請期が延長に 2016/11/10
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が延長になりました。
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
◆定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴 2016/11/04
定年後に再雇用されたトラックの運転手が「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
◆年金受給資格の短縮法案が衆院本会議で可決 2016/11/02
年金が受け取れない人を減らすため、受給資格を得るのに必要な加入期間を、25年から10年に短縮する法案は、1日の衆議院本会議で、全会一致で可決されました。今国会で成立する見通しです。消費増税に先立って来年10月の支払い分から、年金の受給資格を得るのに必要な加入期間を、25年から10年に短縮するとしています。
2016年11月12日
高年齢者の雇用状況
70歳以上まで働ける企業が微増
先日、厚生労働省が、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を公表しました。
それによりますと、「65歳定年」は前年度より0.4ポイント増の14.9%、「定年制の廃止」は0.1ポイント増の2.7%。70歳以上まで働ける企業は1.1ポイント増の21.2%でした。
★調査結果のポイント★
◆1◆ 定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況
定年制の廃止および65歳以上定年企業は計28,541社(対前年差1,472社増加)、割合は18.7%(同0.5ポイント増加)
このうち、
(1)定年制の廃止企業は 4,064社(同 154社増加)
割合は2.7%(同0.1ポイント増加)
(2)65歳以上定年企業は24,477社(同1,318社増加)
割合は16.0%(同0.5ポイント増加)
◆2◆ 希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業の状況
希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業は7,444社(同685社増加)、割合は4.9%(同0.4ポイント増加)
・中小企業では7,147社(同633社増加)5.2%(同0.3ポイント増加)
・大企業では 297社(同 52社増加)1.9%(同0.3ポイント増加)
◆3◆ 70歳以上まで働ける企業の状況
70歳以上まで働ける企業は32,478社(同2,527社増加)、割合は21.2%(同1.1ポイント増加)
・中小企業では30,275社(同2,281社増加)22.1%(同1.1ポイント増加)
・大企業では 2,203社(同 246社増加)13.9%(同1.2ポイント増加)
◇詳細な結果は下記でご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11703000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-Koureishakoyoutaisakuka/0000141160.pdf
★まとめ★
定年廃止や、65歳以上定年の設定にしている会社も増えてきてはいるようですが、「継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講ずる」企業がほとんど(81.3%)のようです。
しかも、301人以上の企業では91.3%とのこと。
つまり、高齢者雇用については、中小企業の方が柔軟に対応しやすいとも言えます。
高齢者と一言でいっても、気力や体力は本当に人それぞれです。大企業を定年で辞めた後の優秀な人材を上手に活用するというのも、中小企業の一つの策です。
この秋、「65歳超雇用推進助成金」なるものも創設されています。この助成金と絡め、高齢者雇用の制度見直しを検討してみてもいいかもしれません。
先日、厚生労働省が、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を公表しました。
それによりますと、「65歳定年」は前年度より0.4ポイント増の14.9%、「定年制の廃止」は0.1ポイント増の2.7%。70歳以上まで働ける企業は1.1ポイント増の21.2%でした。
★調査結果のポイント★
◆1◆ 定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況
定年制の廃止および65歳以上定年企業は計28,541社(対前年差1,472社増加)、割合は18.7%(同0.5ポイント増加)
このうち、
(1)定年制の廃止企業は 4,064社(同 154社増加)
割合は2.7%(同0.1ポイント増加)
(2)65歳以上定年企業は24,477社(同1,318社増加)
割合は16.0%(同0.5ポイント増加)
◆2◆ 希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業の状況
希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業は7,444社(同685社増加)、割合は4.9%(同0.4ポイント増加)
・中小企業では7,147社(同633社増加)5.2%(同0.3ポイント増加)
・大企業では 297社(同 52社増加)1.9%(同0.3ポイント増加)
◆3◆ 70歳以上まで働ける企業の状況
70歳以上まで働ける企業は32,478社(同2,527社増加)、割合は21.2%(同1.1ポイント増加)
・中小企業では30,275社(同2,281社増加)22.1%(同1.1ポイント増加)
・大企業では 2,203社(同 246社増加)13.9%(同1.2ポイント増加)
◇詳細な結果は下記でご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11703000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-Koureishakoyoutaisakuka/0000141160.pdf
★まとめ★
定年廃止や、65歳以上定年の設定にしている会社も増えてきてはいるようですが、「継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講ずる」企業がほとんど(81.3%)のようです。
しかも、301人以上の企業では91.3%とのこと。
つまり、高齢者雇用については、中小企業の方が柔軟に対応しやすいとも言えます。
高齢者と一言でいっても、気力や体力は本当に人それぞれです。大企業を定年で辞めた後の優秀な人材を上手に活用するというのも、中小企業の一つの策です。
この秋、「65歳超雇用推進助成金」なるものも創設されています。この助成金と絡め、高齢者雇用の制度見直しを検討してみてもいいかもしれません。
2016年11月05日
新規学卒者の離職状況
★新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)
先日、厚生労働省が平成25年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について公表しました。
それによりますと、高校卒業者の40%以上、大学卒業者の30%以上が、卒業後3年以内に離職していることが分かったそうです。
大学卒の卒業後3年以内離職率は前年比0.4ポイント減と、若干下がったということですが、規模や業種によっては、3年以内離職率が5割を上回っているところもあります。かなり深刻な状況が伺えます。
下記で詳細な規模別・業種別の数値をお伝えします。
★調査結果のポイント★
◆1◆ 新規学卒者の卒業後3年以内離職率 ( )内は前年比増減
・大学 31.9% (-0.4P)
・短大等 41.7% (+0.2P)
・高校 40.9% (+0.9P)
・中学 63.7% (-1.6P)
◆2◆ 事業所規模別卒業後3年以内離職率
・大学
1,000人以上 23.6% (+0.8P)
500~999人 29.2% (-0.1P)
100~499人 31.9% (-0.3P)
30~99人 38.6% (-0.4P)
5~29人 49.9% (-1.6P)
5人未満 59.0% (-0.6P)
・高校
1,000人以上 24.7% (+3.1P)
500~999人 31.5% (+2.0P)
100~499人 37.9% (+0.9P)
30~99人 47.7% (+0.4P)
5~29人 57.2% (-0.6P)
5人未満 64.4% (-4.0P)
◆3◆ 産業別卒業後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業
・大学
宿泊業・飲食サービス業: 50.5% (-2.7P)
生活関連サービス業・娯楽業:47.9% (-0.3P)
教育・学習支援業: 47.3% (-0.3P)
医療・福祉: 38.4% (+0.4P)
小売業: 51.4% (-0.5P)
・高校
宿泊業・飲食サービス業: 66.1% (-0.1P)
生活関連サービス業・娯楽業:60.5% (-0.6P)
教育・学習支援業: 59.4% (-0.4P)
小売業: 37.5% (-1.0P)
不動産業・物品賃貸業: 48.5% (+0.4P)
★まとめ★
新卒の離職率を下げるためには、メンター制度導入などが効果的と言われています。「メンター制度」などと言うと大企業のもののように思われてしまうかもしれませんが、「先輩がちょっと面倒を見る仕組み」を作るだけで違うはずです。
採用が難しい昨今は特に、離職率を下げることは企業にとって差し迫った課題かと思われます。お気軽にご相談ください。
先日、厚生労働省が平成25年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について公表しました。
それによりますと、高校卒業者の40%以上、大学卒業者の30%以上が、卒業後3年以内に離職していることが分かったそうです。
大学卒の卒業後3年以内離職率は前年比0.4ポイント減と、若干下がったということですが、規模や業種によっては、3年以内離職率が5割を上回っているところもあります。かなり深刻な状況が伺えます。
下記で詳細な規模別・業種別の数値をお伝えします。
★調査結果のポイント★
◆1◆ 新規学卒者の卒業後3年以内離職率 ( )内は前年比増減
・大学 31.9% (-0.4P)
・短大等 41.7% (+0.2P)
・高校 40.9% (+0.9P)
・中学 63.7% (-1.6P)
◆2◆ 事業所規模別卒業後3年以内離職率
・大学
1,000人以上 23.6% (+0.8P)
500~999人 29.2% (-0.1P)
100~499人 31.9% (-0.3P)
30~99人 38.6% (-0.4P)
5~29人 49.9% (-1.6P)
5人未満 59.0% (-0.6P)
・高校
1,000人以上 24.7% (+3.1P)
500~999人 31.5% (+2.0P)
100~499人 37.9% (+0.9P)
30~99人 47.7% (+0.4P)
5~29人 57.2% (-0.6P)
5人未満 64.4% (-4.0P)
◆3◆ 産業別卒業後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業
・大学
宿泊業・飲食サービス業: 50.5% (-2.7P)
生活関連サービス業・娯楽業:47.9% (-0.3P)
教育・学習支援業: 47.3% (-0.3P)
医療・福祉: 38.4% (+0.4P)
小売業: 51.4% (-0.5P)
・高校
宿泊業・飲食サービス業: 66.1% (-0.1P)
生活関連サービス業・娯楽業:60.5% (-0.6P)
教育・学習支援業: 59.4% (-0.4P)
小売業: 37.5% (-1.0P)
不動産業・物品賃貸業: 48.5% (+0.4P)
★まとめ★
新卒の離職率を下げるためには、メンター制度導入などが効果的と言われています。「メンター制度」などと言うと大企業のもののように思われてしまうかもしれませんが、「先輩がちょっと面倒を見る仕組み」を作るだけで違うはずです。
採用が難しい昨今は特に、離職率を下げることは企業にとって差し迫った課題かと思われます。お気軽にご相談ください。
タグ :離職率
2016年10月29日
教育予算は増加傾向
教育研修費用の実態調査
産労総合研究所が、「2016年度(第40回)教育研修費用の実態調査」を実施しました。
それによりますと……
調査回答企業における教育研修費用総額は、2015年度の予算額5,548万円、実績額4,944万円、2016年度の予算額が5,786万円で、前回の2015年度調査と比較するといずれも増加していたとのことです。
採用が難しい今、「すでにいる人を育てる」ことに力を入れ始めた企業も多いのだと思われます。
下記で調査結果のポイントをご紹介します。
★調査結果のポイント★
◆1◆ 教育研修費用総額と従業員1人当たりの教育研修費用
・教育研修費用総額の2015年度の予算額は5,548万円、実績額は4,944万円、2016年度の予算額は5,786万円で、前回調査と比較すると、いずれも増加。
・従業員1人当たりの2015年度実績額は35,662円で、前回調査と比較して約1,200円減少。2016年度予算額は44,892円。こちらも前回調査47,170円と比較して若干減少。
しかし実績額を規模別にみると、中堅企業で37,326円と前回より増加している。
◆2◆ 教育予算の増減状況
・教育予算の対前年比をみると、「増加した」とする企業が54.6%で半数を超えている。平均増加率は33.4%。
◆3◆ 各種教育研修の実施状況
・階層別教育で実施率の高いものとしては、「新入社員教育」が93.5%で例年どおりトップとなった。次いで、「新入社員フォロー教育」77.5%、「初級管理者教育」75.1%、「中堅社員教育」74.0%となっている(複数回答)。
・「職種別・目的別研修」では、「OJT指導員教育」の実施率が49.1%で最も高い。前回実施率の高かった「メンタルヘルス・ハラスメント教育」、「CSR・コンプライアンス教育」は若干減少。
◆4◆ 選抜型リーダー育成制度の取組状況
・選抜型リーダー育成制度を「導入している」企業は38.2%。「導入を予定、または検討中」は13.3%で、あわせて5割強だった。
・課題・問題点としては、「選抜が難しい(人選に課題がある)」が48.1%で最も高い。
◇詳細な結果は下記でご覧いただけます。
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research05/pr_1610/
★まとめ★
調査対象は大手が多いようですが、採用が難しい昨今、「今いる人の能力を最大限に高める」「今いる人の満足度を上げ、離職率を下げる」ことはどんな企業にとっても重要なテーマかと思われます。
産労総合研究所が、「2016年度(第40回)教育研修費用の実態調査」を実施しました。
それによりますと……
調査回答企業における教育研修費用総額は、2015年度の予算額5,548万円、実績額4,944万円、2016年度の予算額が5,786万円で、前回の2015年度調査と比較するといずれも増加していたとのことです。
採用が難しい今、「すでにいる人を育てる」ことに力を入れ始めた企業も多いのだと思われます。
下記で調査結果のポイントをご紹介します。
★調査結果のポイント★
◆1◆ 教育研修費用総額と従業員1人当たりの教育研修費用
・教育研修費用総額の2015年度の予算額は5,548万円、実績額は4,944万円、2016年度の予算額は5,786万円で、前回調査と比較すると、いずれも増加。
・従業員1人当たりの2015年度実績額は35,662円で、前回調査と比較して約1,200円減少。2016年度予算額は44,892円。こちらも前回調査47,170円と比較して若干減少。
しかし実績額を規模別にみると、中堅企業で37,326円と前回より増加している。
◆2◆ 教育予算の増減状況
・教育予算の対前年比をみると、「増加した」とする企業が54.6%で半数を超えている。平均増加率は33.4%。
◆3◆ 各種教育研修の実施状況
・階層別教育で実施率の高いものとしては、「新入社員教育」が93.5%で例年どおりトップとなった。次いで、「新入社員フォロー教育」77.5%、「初級管理者教育」75.1%、「中堅社員教育」74.0%となっている(複数回答)。
・「職種別・目的別研修」では、「OJT指導員教育」の実施率が49.1%で最も高い。前回実施率の高かった「メンタルヘルス・ハラスメント教育」、「CSR・コンプライアンス教育」は若干減少。
◆4◆ 選抜型リーダー育成制度の取組状況
・選抜型リーダー育成制度を「導入している」企業は38.2%。「導入を予定、または検討中」は13.3%で、あわせて5割強だった。
・課題・問題点としては、「選抜が難しい(人選に課題がある)」が48.1%で最も高い。
◇詳細な結果は下記でご覧いただけます。
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research05/pr_1610/
★まとめ★
調査対象は大手が多いようですが、採用が難しい昨今、「今いる人の能力を最大限に高める」「今いる人の満足度を上げ、離職率を下げる」ことはどんな企業にとっても重要なテーマかと思われます。
2016年10月24日
10月のトピックス
◆「介護支援取組助成金」が「介護離職防止支援助成金」に移行 2016/10/20
平成28年度第二次補正予算で創設されたことに伴い、「介護支援取組助成金」が、平成28年10月19日から「介護離職防止支援助成金」に移行されました。これにより、「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに支給要件を満たした事業主が申請できることとなりました。
「介護離職防止支援助成金」は、介護に直面した労働者の支援のため、相談窓口の設置や、労働者が介護休業の取得・職場復帰をした場合や、仕事と介護の両立のための勤務制度を利用した場合等に助成する内容となっています。
移行についての厚労省発表内容の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「介護支援取組助成金の申請について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf
◆ 雇用保険二事業による助成金等の見直し 2016/10/19
平成28年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業による助成金等について、必要な見直しが行われることになりました。
【見直し等の概要】
・再就職支援奨励金の見直し
・受入れ人材育成支援奨励金の見直し
・65歳超雇用推進助成金創設
・生活保護受給者等雇用開発助成金創設
・介護離職防止支援助成金創設(介護支援取組助成金廃止)
・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の見直し
・キャリアアップ助成金見直し
・キャリア形成促進助成金、助成対象訓練追加
・地域活性化雇用創造プロジェクト創設
・地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)暫定措置 など
◆厚労省 建物内の喫煙 罰則付きの規制を検討 2016/10/17
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐため、厚生労働省は、飲食店やホテルなどの建物内を原則禁煙とし、違反した場合は、管理者などに罰金を科す方向で本格的な検討を始めました。
厚生労働省は「受動喫煙の対策は先進国に比べて遅れているのでできるだけ早く対策を強化して4年後の東京オリンピック・パラリンピックまでに定着させたい」としています。
◆外国人技能実習生、異例の過労死認定 残業122時間半 2016/10/17
建設現場や工場などで働く外国人技能実習生が増え続ける中、1人のフィリピン人男性の死が長時間労働による過労死と認定されました。
厚生労働省によると、統計を始めた2011年度以降、昨年度まで認定はなく異例のことです。技能実習生の労働災害は年々増加しています。国会では待遇を改善するための法案が審議されています。
◆初の「過労死白書」を公表 厚生労働省 2016/10/07
おととし施行された過労死防止法に基づいて過労死の実態や防止への取り組み状況を記した初めての「過労死白書」がまとまりました。
過労死等防止対策白書=過労死白書は過労死や過労自殺をなくすため国が防止対策を行うことなどを定めた過労死防止法に基づき、厚生労働省が毎年まとめることにしたもので、7日、初めての白書が閣議決定されました。
白書では過労死や過労自殺の労災が、ここ数年200件前後で推移していることや「過労死ライン」と呼ばれる月80時間を超えて残業した労働者がいる企業の割合が昨年度2割を超えたことを挙げ、長時間労働の是正が課題になっているとしています。そして、過労死の実態を解明するための調査研究として、長時間労働が循環器などの健康に及ぼす影響の研究や労働者の長期的な追跡調査を始めたことなどを報告しています。そのうえで、労働者の相談窓口の設置や継続的な啓発活動を通じて過労死や過労自殺をゼロにすることを目指すと締めくくっています。
平成28年版過労死等防止対策白書【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/index.html
◆厚生年金未加入、最多は卸・小売業(厚労相) 2016/10/05
塩崎厚生労働相は3日の衆院予算委員会で、厚生年金の未加入者について行ったサンプル調査の結果を明らかにしました。業種別では卸売業や小売業が最も多く、次いで製造業、その他サービス業が多い、ということです。
◆長時間労働是正策 「ノー残業デー」が最多 経団連 2016/10/03
政府が「働き方改革」を進める中、経団連が長時間労働の是正に向けた取り組みについて加盟企業に聞いたところ、「ノー残業デーの徹底」が最も多かったのに対して、「朝型勤務」などは導入が進んでいないことがわかりました。
長時間労働を是正する取り組みについて複数回答で聞いたところ、「ノー残業デーの徹底」が最も多く67.8%でした。次いで残業する際はあらかじめ上司に申告する「時間外労働の事前申告制」が67%、残業しなくても済むように「業務の効率化」を進めるが55.2%となっていて、企業の間で、定時で仕事を終える取り組みが広がっていることがうかがえます。
平成28年度第二次補正予算で創設されたことに伴い、「介護支援取組助成金」が、平成28年10月19日から「介護離職防止支援助成金」に移行されました。これにより、「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに支給要件を満たした事業主が申請できることとなりました。
「介護離職防止支援助成金」は、介護に直面した労働者の支援のため、相談窓口の設置や、労働者が介護休業の取得・職場復帰をした場合や、仕事と介護の両立のための勤務制度を利用した場合等に助成する内容となっています。
移行についての厚労省発表内容の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「介護支援取組助成金の申請について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf
◆ 雇用保険二事業による助成金等の見直し 2016/10/19
平成28年度補正予算の成立に伴い、雇用保険二事業による助成金等について、必要な見直しが行われることになりました。
【見直し等の概要】
・再就職支援奨励金の見直し
・受入れ人材育成支援奨励金の見直し
・65歳超雇用推進助成金創設
・生活保護受給者等雇用開発助成金創設
・介護離職防止支援助成金創設(介護支援取組助成金廃止)
・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の見直し
・キャリアアップ助成金見直し
・キャリア形成促進助成金、助成対象訓練追加
・地域活性化雇用創造プロジェクト創設
・地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)暫定措置 など
◆厚労省 建物内の喫煙 罰則付きの規制を検討 2016/10/17
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐため、厚生労働省は、飲食店やホテルなどの建物内を原則禁煙とし、違反した場合は、管理者などに罰金を科す方向で本格的な検討を始めました。
厚生労働省は「受動喫煙の対策は先進国に比べて遅れているのでできるだけ早く対策を強化して4年後の東京オリンピック・パラリンピックまでに定着させたい」としています。
◆外国人技能実習生、異例の過労死認定 残業122時間半 2016/10/17
建設現場や工場などで働く外国人技能実習生が増え続ける中、1人のフィリピン人男性の死が長時間労働による過労死と認定されました。
厚生労働省によると、統計を始めた2011年度以降、昨年度まで認定はなく異例のことです。技能実習生の労働災害は年々増加しています。国会では待遇を改善するための法案が審議されています。
◆初の「過労死白書」を公表 厚生労働省 2016/10/07
おととし施行された過労死防止法に基づいて過労死の実態や防止への取り組み状況を記した初めての「過労死白書」がまとまりました。
過労死等防止対策白書=過労死白書は過労死や過労自殺をなくすため国が防止対策を行うことなどを定めた過労死防止法に基づき、厚生労働省が毎年まとめることにしたもので、7日、初めての白書が閣議決定されました。
白書では過労死や過労自殺の労災が、ここ数年200件前後で推移していることや「過労死ライン」と呼ばれる月80時間を超えて残業した労働者がいる企業の割合が昨年度2割を超えたことを挙げ、長時間労働の是正が課題になっているとしています。そして、過労死の実態を解明するための調査研究として、長時間労働が循環器などの健康に及ぼす影響の研究や労働者の長期的な追跡調査を始めたことなどを報告しています。そのうえで、労働者の相談窓口の設置や継続的な啓発活動を通じて過労死や過労自殺をゼロにすることを目指すと締めくくっています。
平成28年版過労死等防止対策白書【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/index.html
◆厚生年金未加入、最多は卸・小売業(厚労相) 2016/10/05
塩崎厚生労働相は3日の衆院予算委員会で、厚生年金の未加入者について行ったサンプル調査の結果を明らかにしました。業種別では卸売業や小売業が最も多く、次いで製造業、その他サービス業が多い、ということです。
◆長時間労働是正策 「ノー残業デー」が最多 経団連 2016/10/03
政府が「働き方改革」を進める中、経団連が長時間労働の是正に向けた取り組みについて加盟企業に聞いたところ、「ノー残業デーの徹底」が最も多かったのに対して、「朝型勤務」などは導入が進んでいないことがわかりました。
長時間労働を是正する取り組みについて複数回答で聞いたところ、「ノー残業デーの徹底」が最も多く67.8%でした。次いで残業する際はあらかじめ上司に申告する「時間外労働の事前申告制」が67%、残業しなくても済むように「業務の効率化」を進めるが55.2%となっていて、企業の間で、定時で仕事を終える取り組みが広がっていることがうかがえます。
2016年10月15日
勤労生活に関する調査~★~「終身雇用」を支持する割合が過去最高
独立行政法人労働政策研究・研修機構が「第7回勤労生活に関する調査」を行い、結果を公表しました。
多くの人が1つの会社で長く働きたいと思っているなど、働く人の「今」が見える調査結果でしたので、参考にして頂けたらと思います。
★調査結果のポイント★
1.「終身雇用」を支持する割合が約9割で、過去最高
・「終身雇用」を支持する者の割合は、調査を開始した1999年以降、過去最高の87.9%
・「組織との一体感」「年功賃金」を支持する割合もそれぞれ、88.9%、76.3%と過去最高の高水準。
・いわゆる日本型雇用慣行をあらわす項目に対する支持割合が上昇している。とくに20~30 歳代で、「終身雇用」「年功賃金」の支持割合が2007年から急激に伸びており、年齢階層による違いがあまりみられなくなった。
2.過半数が1つの企業に長く勤める働き方を望んでいる
・1つの企業に長く勤め管理的な地位や専門家になるキャリアを望む者(「一企業キャリア」)の割合は50.9%と過半数。
・2007年調査では年齢階層別でもっとも支持率が低かった20歳代が、今回調査では54.8%ともっとも高い支持率となっているのが目立つ。
・時系列に見ると、「一企業キャリア」を選択する割合がゆるやかな上昇傾向を示す一方、「複数企業キャリア」「独立自営キャリア」を望む割合は、低下傾向を示している。
3.女性の「職場進出」「社長」「管理職」の増加に、抵抗を感じる男性は1割
・女性の「職場進出」「社長」「管理職」が増えることに、抵抗を感じる割合は1割前後。男女別に見ても差はわずか。
・「乳幼児を他人にあずけて母親が働きにでること」については、「抵抗感がある」(48.6%)と「抵抗感がない」(48.4%)がほぼ拮抗。これも男女で大きな差がなく、女性でも「抵抗感がある」が47.3%と過半数に迫る水準となっている。
4.どの年齢階層でも、いくつになっても働ける社会にしたいと考えている人が大多数
・9割強が「年齢にかかわりなく働ける社会が望ましい」と回答。20歳代、30歳代の若年者でもそう考える人が大多数(それぞれ85.4%、90.2%)。
・その一方で、20歳代で「高齢者は早めに引退して、若年者の雇用機会を確保した方がよい」と考える割合が49.0%と約半数を占め、他の年齢階層が軒並み3割半ばなのに比べて突出して高くなっているのが目立つ。
>> 調査の詳細は下記でご覧いただけます。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20160923.pdf
★まとめ★
終身雇用や年功賃金に対する支持割合が過去最高になったということですが、この「1つの企業で、安定して働きたい」という風潮が、ここ数年の日本のトレンドのようです。
新卒社員を採るときなどは、そのあたりの魅力をアピールする必要も出てくるのかもしれません。
最近、介護休業を取らせた企業に対する助成金新設の情報なども出ていますが、育児だけではなく、介護が必要な時期も支え、「長く働いてもらえる環境を作る」ということが、労使ともの幸せにつながるようにも感じます。
是非そのような助成金情報と一緒に、「今、働く人が何を求めているのか」の情報も、弊事務所にご相談いただき、今後の経営にお役立てください。
多くの人が1つの会社で長く働きたいと思っているなど、働く人の「今」が見える調査結果でしたので、参考にして頂けたらと思います。
★調査結果のポイント★
1.「終身雇用」を支持する割合が約9割で、過去最高
・「終身雇用」を支持する者の割合は、調査を開始した1999年以降、過去最高の87.9%
・「組織との一体感」「年功賃金」を支持する割合もそれぞれ、88.9%、76.3%と過去最高の高水準。
・いわゆる日本型雇用慣行をあらわす項目に対する支持割合が上昇している。とくに20~30 歳代で、「終身雇用」「年功賃金」の支持割合が2007年から急激に伸びており、年齢階層による違いがあまりみられなくなった。
2.過半数が1つの企業に長く勤める働き方を望んでいる
・1つの企業に長く勤め管理的な地位や専門家になるキャリアを望む者(「一企業キャリア」)の割合は50.9%と過半数。
・2007年調査では年齢階層別でもっとも支持率が低かった20歳代が、今回調査では54.8%ともっとも高い支持率となっているのが目立つ。
・時系列に見ると、「一企業キャリア」を選択する割合がゆるやかな上昇傾向を示す一方、「複数企業キャリア」「独立自営キャリア」を望む割合は、低下傾向を示している。
3.女性の「職場進出」「社長」「管理職」の増加に、抵抗を感じる男性は1割
・女性の「職場進出」「社長」「管理職」が増えることに、抵抗を感じる割合は1割前後。男女別に見ても差はわずか。
・「乳幼児を他人にあずけて母親が働きにでること」については、「抵抗感がある」(48.6%)と「抵抗感がない」(48.4%)がほぼ拮抗。これも男女で大きな差がなく、女性でも「抵抗感がある」が47.3%と過半数に迫る水準となっている。
4.どの年齢階層でも、いくつになっても働ける社会にしたいと考えている人が大多数
・9割強が「年齢にかかわりなく働ける社会が望ましい」と回答。20歳代、30歳代の若年者でもそう考える人が大多数(それぞれ85.4%、90.2%)。
・その一方で、20歳代で「高齢者は早めに引退して、若年者の雇用機会を確保した方がよい」と考える割合が49.0%と約半数を占め、他の年齢階層が軒並み3割半ばなのに比べて突出して高くなっているのが目立つ。
>> 調査の詳細は下記でご覧いただけます。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20160923.pdf
★まとめ★
終身雇用や年功賃金に対する支持割合が過去最高になったということですが、この「1つの企業で、安定して働きたい」という風潮が、ここ数年の日本のトレンドのようです。
新卒社員を採るときなどは、そのあたりの魅力をアピールする必要も出てくるのかもしれません。
最近、介護休業を取らせた企業に対する助成金新設の情報なども出ていますが、育児だけではなく、介護が必要な時期も支え、「長く働いてもらえる環境を作る」ということが、労使ともの幸せにつながるようにも感じます。
是非そのような助成金情報と一緒に、「今、働く人が何を求めているのか」の情報も、弊事務所にご相談いただき、今後の経営にお役立てください。